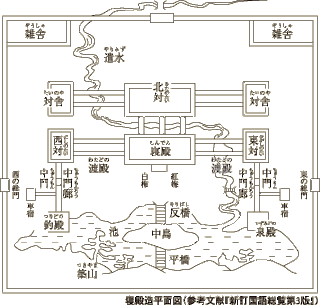- 奈良時代
- 当時、唐の最盛期。世界最大の都市・長安から仏教を根幹としてあらゆる文化が輸入された。
平城京・東大寺・法隆寺など
- 当時、唐の最盛期。世界最大の都市・長安から仏教を根幹としてあらゆる文化が輸入された。
- 平安時代
- 貴族文化が爛熟した時代。末法思想の広まりとともに阿弥陀信仰が流行した。現存するこの時代の建物だと、平等院鳳凰堂など、極楽のイメージを空間化するテーマパークのようなものが生まれる。中期に遣唐使が廃止され、独自の曲線を多用した優雅で精緻な特徴をもつ造形を展開した
- 貴族文化が爛熟した時代。末法思想の広まりとともに阿弥陀信仰が流行した。現存するこの時代の建物だと、平等院鳳凰堂など、極楽のイメージを空間化するテーマパークのようなものが生まれる。中期に遣唐使が廃止され、独自の曲線を多用した優雅で精緻な特徴をもつ造形を展開した
- 鎌倉・室町時代
- 政治の中心は鎌倉へ。新興勢力の武士は貴族的なものを嫌い、密教を遠ざけ、変わりに自分達の思想的なバックボーンとしてこれまた新興一派である禅宗を重用した。ここに、現在の茶道の歴史が始まる。遣唐使廃止後、このころから宋との交易がさかんになり、入手困難な舶来品を手に入れた人がそれを自分で見る/他人に見せるためにインテリアの概念が意識されるようになり、現代の和室の基本的構造やモジュールがこの時代に定まる。
慈照寺(銀閣寺)東求堂同仁斎・東福寺
- 政治の中心は鎌倉へ。新興勢力の武士は貴族的なものを嫌い、密教を遠ざけ、変わりに自分達の思想的なバックボーンとしてこれまた新興一派である禅宗を重用した。ここに、現在の茶道の歴史が始まる。遣唐使廃止後、このころから宋との交易がさかんになり、入手困難な舶来品を手に入れた人がそれを自分で見る/他人に見せるためにインテリアの概念が意識されるようになり、現代の和室の基本的構造やモジュールがこの時代に定まる。
- 安土桃山時代
- 下剋上の戦国時代。南蛮文化の流入により、価値基準が増える。この時代までは唐物が尊重されてきたが、そのアンチテーゼとして国産の茶道具を取り入れ、格式ばった書院づくりからはなれて、数寄屋(田舎屋風の極小空間)で少人数が参加する茶のスタイルを提示したのが新しい。
- 下剋上の戦国時代。南蛮文化の流入により、価値基準が増える。この時代までは唐物が尊重されてきたが、そのアンチテーゼとして国産の茶道具を取り入れ、格式ばった書院づくりからはなれて、数寄屋(田舎屋風の極小空間)で少人数が参加する茶のスタイルを提示したのが新しい。
- 寝殿造庭園
- 平安~鎌倉時代に貴族がつくった遊興の舞台となる庭。儀式や歌会など、行為と政治のための庭
- 浄土式庭園
- 仏教の浄土思想の影響を大きく受けたもの。平等院鳳凰堂に代表されるように、極楽浄土の世界を再現しようとしたため金堂や仏堂をはじめとした寺院建築物の前に園池が広がる形をとっている。
- 寝殿造庭園で遊興を楽しんでいた貴族達は、庭園内に阿弥陀仏を祀る阿弥陀堂をつくったり、これらの屋敷を寺院に寄進することで心の平安を得ようとした。浄土庭園が、殿舎の南に広がる大きな池、水辺の石組や築山、橋の架かる中島を備えている。骨格において寝殿造庭園と全く共通するのはこのため。
- 京都府宇治市 平等院
- 京都府木津川市 浄瑠璃寺
- 仏教の浄土思想の影響を大きく受けたもの。平等院鳳凰堂に代表されるように、極楽浄土の世界を再現しようとしたため金堂や仏堂をはじめとした寺院建築物の前に園池が広がる形をとっている。
- 枯山水庭園
- 平安末期以降の動乱の世にあって、仏教が広く民衆に浸透していった鎌倉・室町時代に、遣水などの水を用いることなく、石組みを主にして、砂、樹木などで山水を表現する庭園が、修行環境として仏教施設に取り入れられ洗練されていった。個人救済の仏教を模索して、山林にこもり自己と対峙して人間の内面を深く追求した修行僧の、純粋な抽象的思考を妨げない環境づくりとして生まれた。
- 龍安寺方丈の石庭
- 妙心寺東海庵
- 大徳寺大仙院の庭
- 南禅寺・金地院の庭
- 平安末期以降の動乱の世にあって、仏教が広く民衆に浸透していった鎌倉・室町時代に、遣水などの水を用いることなく、石組みを主にして、砂、樹木などで山水を表現する庭園が、修行環境として仏教施設に取り入れられ洗練されていった。個人救済の仏教を模索して、山林にこもり自己と対峙して人間の内面を深く追求した修行僧の、純粋な抽象的思考を妨げない環境づくりとして生まれた。
- 書院式庭園
- 鎌倉時代になると、貴族・武士階級の住宅建築は寝殿造りから書院造りに変化し、それに伴い庭園も建物に隣接した書院造りに変わっていた。書院式庭園は 寝殿造庭園に比べて小さく作りも簡素だが、基本的には浄土式庭園に近い形態が引き継がれている。
- 建物の中から庭園を見るという、視線の方向と範囲を意識してつくられた。
- 巨大な庭石と色彩豊かな色石などを多く使用し、枯山水にみられるような抽象化とは反対に心地良い自然の具象化が求められるようになった。当時、庭石は権力の象徴、権力誇示のデモンストレーションのための道具として利用された。
- 醍醐寺三宝院庭園
- 西本願寺大書院庭園
- 鎌倉時代になると、貴族・武士階級の住宅建築は寝殿造りから書院造りに変化し、それに伴い庭園も建物に隣接した書院造りに変わっていた。書院式庭園は 寝殿造庭園に比べて小さく作りも簡素だが、基本的には浄土式庭園に近い形態が引き継がれている。
- 露地・茶庭
- 「露地」とは茶室へと向かう道程そのものを指す。狭く限られた空間に造られ、市中の山居、都市の中にありながら世俗を離れた深山を想起させる工夫がある。都市の喧騒を逃れ、山里に隠遁するのを理想とする考え方は、室町時代以前にもあったが、これをひとつの美意識にまで高めたのが、安土桃山時代に千利休によって大成されたわび茶。「浮世(うきよ)の外ノ道」と利休により表現された露地は、茶の湯という非日常の世界を茶室とともにある。
- 用(実用)と景(景観美)を併せ持つ、茶室と一体となった空間を追求していく中で、露地は、飛石・延段・石燈篭・手水鉢など、後世の庭園造りに欠かせない要素を機能的に組み込んでいった。
既成概念にとらわれない数寄の感性によって、非日常的な遊びや感動を楽しむための様々な工夫が取り入れられ、江戸時代には次第に様式化されていくが、京都の町家にある坪庭や玄関庭のしつらえには、今も茶庭の手法が基本になっている。
- 龍安寺方丈の石庭
- 妙心寺東海庵
- 大徳寺大仙院の庭
- 南禅寺・金地院の庭
- 「露地」とは茶室へと向かう道程そのものを指す。狭く限られた空間に造られ、市中の山居、都市の中にありながら世俗を離れた深山を想起させる工夫がある。都市の喧騒を逃れ、山里に隠遁するのを理想とする考え方は、室町時代以前にもあったが、これをひとつの美意識にまで高めたのが、安土桃山時代に千利休によって大成されたわび茶。「浮世(うきよ)の外ノ道」と利休により表現された露地は、茶の湯という非日常の世界を茶室とともにある。
- 回遊式庭園
- 江戸時代、遊興の場として積極的に使われた社交場。武家・公家社会を問わず、社交の場としての空間。園内を回遊する様式の庭園で、部分的に異なった自然風景を描き出し、計算し尽くしたもてなしが行える舞台装置として造園された。江戸時代の大規模な庭園はすべてこの様式。
- 本願寺の渉成園もこの様式。江戸前期、徳川家光が東本願寺にこの地を与え、庭に石川丈山が池泉を築き、以降回遊式の代表的な庭とされている。この他、日本各地に残る回遊式庭園の大名庭園は、茶の湯・能・狂言・連歌・俳諧など当時の芸能・芸術活動の舞台であり、また鴨猟・乗馬・弓術・釣りなどのスポーツまで引き受ける幅広い性格を持っていた。
- 桂離宮
- 修学院離宮
- 平安神宮
- 江戸時代、遊興の場として積極的に使われた社交場。武家・公家社会を問わず、社交の場としての空間。園内を回遊する様式の庭園で、部分的に異なった自然風景を描き出し、計算し尽くしたもてなしが行える舞台装置として造園された。江戸時代の大規模な庭園はすべてこの様式。
歴史
庭
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------